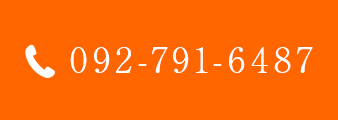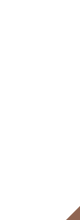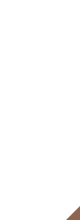ブログ
歯の黄ばみ~原因を知って始める効果的な対策と予防法を専門医が解説します
歯の黄ばみが気になる方へ~原因を知ることから始めましょう
鏡を見たとき、自分の歯の色が黄ばんでいることに気づいて、ふと笑顔に自信がなくなった経験はありませんか?
歯の黄ばみは多くの方が抱える悩みです。実際、ある調査では成人男女200人のうち186人が「歯の黄ばみが気になったことがある」と回答しています。つまり、ほとんどの人が歯の色に何らかの不安を感じているのです。

歯の黄ばみには様々な原因があり、その対策方法も原因によって異なります。適切なケアを行うためには、まず自分の歯がなぜ黄ばんでいるのかを知ることが大切です。
今回は歯科医師として長年患者さんの歯の悩みと向き合ってきた経験から、歯の黄ばみの原因と効果的な対策方法についてお伝えします。
歯の黄ばみが起こる主な原因とメカニズム
歯の黄ばみは大きく分けて「外因性」と「内因性」の2つに分類できます。それぞれの原因を理解することで、効果的な対策方法が見えてきます。
外因性の黄ばみ~日常生活が歯の色に与える影響
外因性の黄ばみとは、歯の表面に色素が付着することで起こる変色のことです。主な原因は以下の通りです。
飲食物による着色
コーヒー、紅茶、赤ワイン、チョコレートなどに含まれるタンニンやポリフェノールは、歯の表面に付着しやすい性質を持っています。これらの成分が歯の表面にある薄い膜(ペリクル)と結びつくと、「ステイン」と呼ばれる着色汚れになります。
カレーやしょうゆなどの色の濃い食品も同様に、歯を黄ばませる原因となります。
タバコによる着色
タバコに含まれるタールやニコチンは、歯の表面に黄褐色の着色を引き起こします。喫煙者の歯が黄ばみやすいのはこのためです。
タバコのヤニは粘着性が高いため、一度付着すると簡単には落ちません。半日から1日程度放置すると歯にこびりついてしまい、通常の歯磨きでは落としにくくなります。
口腔内の乾燥と歯垢・歯石
口呼吸や唾液の減少による口腔内の乾燥も、歯の黄ばみに関係しています。唾液には自然な洗浄作用があるため、口が乾燥すると歯の汚れが付着しやすくなります。
また、歯磨きが不十分だと、歯の表面にプラーク(歯垢)が形成されます。このプラークが石灰化すると歯石となり、黄ばみの原因になります。特に歯と歯の間や歯ぐきとの境目は、歯ブラシが届きにくいため注意が必要です。

内因性の黄ばみ~歯の内部から生じる変色
内因性の黄ばみは、歯の内部構造に関係する変色です。
歯の構造と加齢による変化
歯は外側の「エナメル質」と内側の「象牙質」という組織で構成されています。エナメル質は半透明で、内側にある象牙質の色が透けて見えるのが自然な状態です。
象牙質は乳白色から黄色味を帯びた色をしており、年齢を重ねるにつれて色が濃くなります。同時に、エナメル質は徐々に薄くなっていくため、加齢とともに歯は黄ばんで見えるようになります。
これは自然な現象であり、完全に防ぐことは難しいのです。
日本人の歯はもともと黄色い?人種による違い
「外国の方の歯は白くてきれいなのに、日本人の歯はなぜ黄ばみやすいの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、歯の色や特徴は人種によって異なります。日本人を含むアジア人は、白人と比べるとエナメル質が薄く、象牙質の色が透けやすい傾向があるのです。
歯の色を表すシェードガイドという指標では、日本人の歯は平均してA3前後と言われています。対して白人はA2〜A1とされており、もともとの色が異なるのです。
また、海外では日本のような健康保険制度がない国も多く、虫歯や歯周病の治療費が高額になります。そのため、予防歯科に通うことが習慣化されている国も多く、定期的に歯石や着色を落としているケースが多いことも、外国人の歯が白く見える理由の一つと考えられます。
歯の黄ばみを改善する効果的な対策方法
歯の黄ばみの原因がわかったところで、具体的な対策方法を見ていきましょう。黄ばみの種類によって効果的な方法が異なります。
外因性の黄ばみへの対策
正しい歯磨き習慣の確立
外因性の黄ばみ対策の基本は、正しい歯磨き習慣です。1か所につき約10回のブラッシングを行い、全体で3分程度かけることが推奨されています。特に歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間は丁寧に磨きましょう。
歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシを使用することで、歯ブラシの届かない部分の汚れも効果的に除去できます。
歯磨きのタイミングも重要です。食後すぐに磨くと、酸によって柔らかくなったエナメル質を傷つける可能性があるため、食後30分程度経ってから磨くことをお勧めします。
どうですか?今の歯磨き習慣を見直すきっかけになりましたか?
ホワイトニング歯磨き粉の活用
市販のホワイトニング歯磨き粉には、歯の表面の汚れを落とす効果があります。配合成分によって効果が異なるため、自分の歯の状態に合わせて選ぶことが大切です。
ハイドロキシアパタイトは歯の表面の傷を埋めて整える効果があり、ポリリン酸ナトリウムは着色汚れを浮かせて除去する働きがあります。
ただし、研磨剤の強い歯磨き粉を長期間使用すると、エナメル質を傷つける可能性があるため注意が必要です。歯科医院で自分に合った製品を相談するのがベストです。
歯科医院での専門的なケアと治療法
自宅でのケアだけでは落としきれない黄ばみには、歯科医院での専門的な治療が効果的です。
プロフェッショナルクリーニング
歯科医院でのクリーニングでは、専用の機器を使って歯石や着色汚れを除去します。エアフローという装置を使えば、歯磨きでは落としきれない頑固な着色も効果的に落とすことができます。
定期的なクリーニングは、歯の黄ばみ予防だけでなく、虫歯や歯周病の予防にもつながります。半年に一度のペースで受けることをお勧めします。
当院でも、患者さんの歯の状態に合わせた丁寧なクリーニングを行っています。特に着色が気になる方には、エアフローを使用した徹底的なクリーニングをご提案しています。
ホワイトニング治療
もともとの歯の色を明るくしたい場合は、ホワイトニング治療が効果的です。ホワイトニングには大きく分けて以下の種類があります。
オフィスホワイトニング:歯科医院で行う治療で、高濃度の薬剤を使用するため、短時間で効果が得られます。即効性を求める方に適しています。
ホームホワイトニング:歯科医院で作製したマウスピースに薬剤を入れ、自宅で行うホワイトニングです。低濃度の薬剤を使用するため、オフィスホワイトニングより時間はかかりますが、歯への負担が少なく、効果が長持ちする傾向があります。
デュアルホワイトニング:オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせた方法で、より効果的に歯を白くすることができます。
ホワイトニング治療は、外因性の着色だけでなく、内因性の黄ばみにも効果があります。ただし、すべての方に適しているわけではないため、事前に歯科医師の診断を受けることが重要です。

歯の黄ばみを予防するための日常習慣
歯を白く保つためには、日々の予防習慣が何より大切です。以下のポイントを意識して、美しい歯を維持しましょう。
着色しやすい食べ物・飲み物への対策
コーヒーや紅茶、赤ワインなどの着色しやすい飲み物を摂取した後は、すぐに水でうがいをすることで、色素が歯に付着するのを防ぐことができます。
ストローを使用すると、飲み物が歯に直接触れる機会が減るため、着色予防に効果的です。特に紅茶やコーヒーなどを飲む際は、ストローの使用を検討してみてください。
また、チーズやりんごなどの食品には、自然な歯の洗浄効果があります。着色しやすい食べ物を摂取した後に、これらの食品を食べると良いでしょう。
あなたは普段、飲み物を飲んだ後にうがいをする習慣はありますか?

唾液の分泌を促す工夫
唾液には自然な洗浄作用があるため、唾液の分泌を促すことも歯の黄ばみ予防に効果的です。
キシリトール配合のガムを噛むことで、唾液の分泌が促進されます。また、よく噛んで食事をすることも唾液の分泌を増やし、口腔内を清潔に保つのに役立ちます。
水分をこまめに摂取することも、口腔内の乾燥を防ぎ、歯の健康を維持するために重要です。特に就寝中は唾液の分泌が減少するため、寝る前の歯磨きは丁寧に行いましょう。
やってはいけない!歯の黄ばみ対策の注意点
インターネットなどで紹介されている歯を白くする方法の中には、歯に悪影響を及ぼす可能性のあるものもあります。以下の方法は避けるべきです。
重曹で磨く
重曹は研磨作用が強く、頻繁に使用するとエナメル質を傷つける可能性があります。一時的に歯が白く見えても、長期的には歯の健康を損なう恐れがあるため、おすすめできません。
レモン汁や酢などの酸性の液体で磨く
酸性の液体はエナメル質を溶かす作用があります。これらを使用すると、一時的に歯が白く見えることがありますが、エナメル質が薄くなり、かえって象牙質の黄色が透けやすくなる可能性があります。
メラミンスポンジで磨く
キッチン用のメラミンスポンジは非常に細かい研磨剤の役割を果たし、エナメル質を削ってしまいます。また、口腔内に使用するものではないため、健康上のリスクもあります。
これらの方法は一時的な効果があるように見えても、長期的には歯を傷つけ、かえって黄ばみやすくなる原因となります。歯の健康を守るためには、歯科医師の指導のもとで適切なケアを行うことが大切です。
まとめ~美しい白い歯を手に入れるために
歯の黄ばみは、外因性と内因性のさまざまな要因によって引き起こされます。コーヒーやタバコなどによる外因性の着色は、適切なケアで改善できる可能性が高いですが、加齢や遺伝による内因性の黄ばみには専門的な治療が必要な場合があります。
日常的なケアとしては、正しい歯磨き習慣の確立、着色しやすい食べ物・飲み物の摂取後のうがい、定期的な歯科検診とクリーニングが効果的です。また、必要に応じてホワイトニング治療を検討することも選択肢の一つです。
美しい白い歯は、自信に満ちた笑顔をもたらし、対人関係においても良い印象を与えます。しかし、無理な自己流のケアは歯を傷つける可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な方法で歯の健康と美しさを保つことが大切です。
当院では、患者さん一人ひとりの歯の状態に合わせたオーダーメイドの治療計画を提案しています。歯の黄ばみでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの素敵な笑顔をサポートいたします。
【著者】別府 優子 べっぷゆうこ歯科・矯正クリニック 院長
九州大学歯学部卒業後、複数の歯科医院にて一般歯科および矯正治療の臨床経験を積む。
「すべての患者様が安心して通える歯科医院」を理念に掲げ、患者様一人ひとりの口腔状態に合わせた治療計画を重視している。
歯周病・インプラント・矯正治療・マイクロスコープ治療など、幅広い分野の研鑽を続けながら、患者様の「自分の歯を長く守る」ためのサポートに力を注いでいる。
主な所属・修了コース
WDC(女性歯科医師の会)所属
船越歯科歯周病研究所 ベーシックコース/マスターコース修了
Just Post Graduate 10ヶ月コース修了
下川公一臨床セミナー アドバンスコース受講
近未来オステオインプラント学会
日本臨床歯周病学会
日本顎咬合学会
日本歯科東洋医学会
日本顕微鏡歯科学会
経基臨塾
日本矯正歯科学会